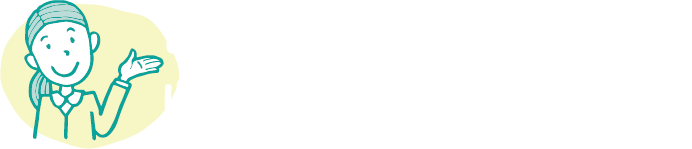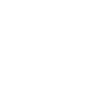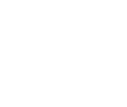助成金情報
環境省
この助成事業は募集期間を終了しています。
令和6年度補正予算 消費者の行動変容等による家庭系食品ロスの削減推進モデル事業 二次公募
対象分野
![]() 環境の保全を図る活動
環境の保全を図る活動
対象エリア
日本国内
助成の目的
本モデル事業は、家庭系の食品ロス削減に効果があると思われる地方公共団体や事業者等の取組を支援し、その成果を広く発信することを通して、家庭系食品ロス削減目標の早期に達成することを目的とする。
助成金額
一時公募と合わせ、支援総額は5,000万円(税込)
総額内で10件程度の採択を予定
対象事業
◆家庭系食品ロス削減に関するモデル事業
本モデル事業は、一般家庭から排出される食品ロス削減を実現するモデルを創出する。
具体的には、本モデル事業期間内に必ず食品ロス削減を(期間限定であっても)達成し、家庭系食品ロス削減に係る課題整理、取組の実施に伴う効果検証(導入前後の食品ロス等の発生量の比較等の定量的な検証等)、事業継続に向けたスキーム検討、普及啓発資材の活用、関係主体との連携・調整等に対し、その費用の支援および技術的支援を行うものである。
なお、モデル実施事業者には、令和6年度に環境省が作成した「~自治体・事業者向け~消費者の行動変容等による食品ロスの効果的な削減に向けた手引き」を送付する。事業実施に当たっては、令和7年度中に見直しを予定する本手引きを参照するものとし、環境省および事務局請負事業者はモデル実施事業者に対し、必要に応じたヒアリングを実施する。
<具体的なテーマ例>
①ごみ分別アプリを活用した食品ロス削減に関する情報発信(冷蔵庫整理等)
自治体に広く導入されるごみ分別アプリの情報発信機能やプッシュ通知等により、食品ロス削減に向けた行動のうち「タイムリーな介入が効果的と考えられるメッセージ(定期的な冷蔵庫整理等)」と「使い切り・食べ切り」を促し、介入効果を測定する。
②健康の増進に着目した適量調理や適量配膳の訴求
食べ残し削減のための工夫である「適量調理」や「適量配膳」は、食べ過ぎ防止等により健康増進に役立つ側面もある。料理レシピアプリ・サイト、ワークショップ等により適量調理や適量配膳の普及促進を図り、あわせて健康増進のメッセージを訴求することによる効果を測定する。
③家庭から出る余剰食品(自家栽培野菜 等)の寄附の促進
市町村が媒介となって地域の市民農園と近隣の食支援団体(こども食堂等)をマッチングし、市民農園にて不定期に発生する余剰野菜の寄附活用や家庭内の余剰食品を寄附するフードドライブの取組を促進する。マッチングに向けた調整や運搬方法等の諸課題に対する対応を整理することで、他市町村にとって参考となるモデルケースを創出する。
④食事購入履歴の見える化による買い物行動の最適化
電子シート情報等をもとに、食材購入履歴をスマホアプリ等で確認、自宅にストックされている食材の種類や量を把握・類推できるようにする。店舗での食材購入時にアプリで履歴を確認することで、"必要なもの”を"必要な量”だけ入手。家庭での食品ロスさくげん、支出抑制(節約)効果を実証する。
⑤食品小売店での量り売り・ばら売りによる買い物行動の最適化
食品小売店での青果物等の販売時に、量り売り・ばら売りを行い、消費者が"必要なもの”を"必要な量”だけを購入できるよう行動変容を促す。小ロット・小分け販売と同様の考え方で、適切な食材調達を支援し、家庭系食品ロス削減と節約効果を実証する。
※あくまで一例であり、事業規模の大小を問わず、地域の実情に応じた多様な提案が対象事業となりうる。
◆事業実施期間
選定結果の通知後から令和8年1月30日まで
対象者
申請者は、地方公共団体や事業者等を原則とする。ただし、複数の地方公共団体や事業者等が共同で提案することを妨げない。
募集期間
2025年5月23日(金)まで 18:00必着
申込み・応募方法
添付資料2の様式による申請書に必要事項を記入の上、申請書一式を添付して、電子メールで提出すること。
問い合わせ先団体情報
問い合わせ先団体名
環境省環境再生・資源循環局総務課リサイクル推進室
担当者名
食品ロス・食品リサイクル担当(小田戸・常住)
郵便番号
100-8975
住所
東京都千代田区霞が関1-2-2
電話番号
03-6205-4946(可能な限りemailで問い合わせること)
メールアドレス
hairi-recycle@env.go.jp