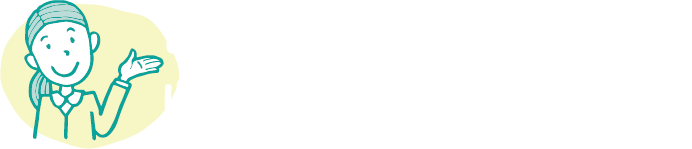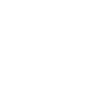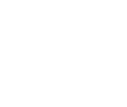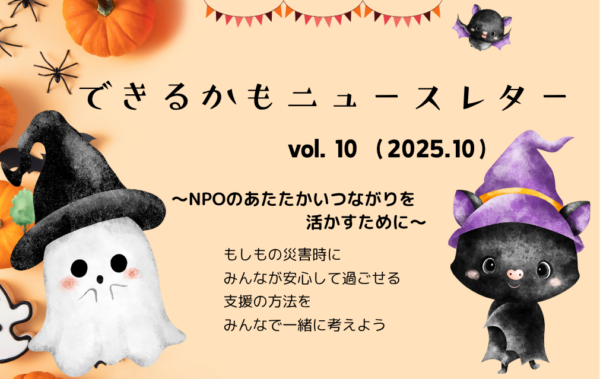お知らせ
できるかもニュースレター〈vol.10〉2025.10
~NPOのあたたかいつながりを活かすために~
もしもの災害時にも、安心して過ごせる支援の方法を一緒に考えよう
————————————————————————————
◇できるかもニュースレター vol.10(2025.10)◆
*ごあいさつ*
みなさん、こんにちは!
先日、新潟で開催された「ぼうさいこくたい2025」にセンタースタッフも参加してきました。
企業やNPO、大小さまざまな団体が集まり、意外な出会いや気づきもいっぱい。
「自分の備えって、本当はどうなんだろう?」と改めて考えさせられました。
今月号も、そんな「気づき」をみなさんと共有できたら嬉しいです。
————————————————————————————-
🌻CONTENTS🍉
〜新潟からオールジャパンで進める防災・減災〜
◆性的マイノリティって?「多様性配慮ガイドライン」を学ぶ
◆しものせき防災フェスタ2025
~備えと安心のための・体験・学び・交流~
◆ぼうさい活動に関する支援制度・助成金情報
————————————————————————————-
☆ぼうさいこくたい2025in新潟
〜新潟からオールジャパンで進める防災・減災〜
新潟駅に降り立つと、駅は改装工事の真っ最中。
周辺の飲食街は、ぼうさいこくたい開催のためか、夕方にはどこも満席続きで入店待ちが出るほどのにぎわいでした。
それでも朱鷺メッセ方面へ向かう道すがら、信濃川と日本海の風が混じるようなさわやかさも感じられ、
ぼうさいこくたいの「学びながら・遊びながら備える」ムードの高まりも実感。
2004年の中越地震を経験した新潟で、9月6日・7日と記念すべき第10回「ぼうさいこくたい」が開催されました。
会場にはお子様連れもたくさん訪れ、楽しみながら防災を学ぶことができる、まさにお祭りのような雰囲気!
屋外・屋内にはたくさんの団体や企業の展示が並び、災害対応の取り組みや商品を見学することができました。
液状化実験やペットの災害食、巨大迷路などのユニークな体験展示もあり、来場者の関心を集めていました。
【印象的だったセッション】
7日の午後からは、JVOAD主催のセッション「能登半島地震の事例から支援で目指す姿を考える」に参加しました。
子ども支援・地域コミュニティ支援・ペットがいる世帯支援の3つの観点から、
災害時に本当に必要とされる支援のあり方を考えました。
登壇者は、新潟県社会福祉協議会、ワールド・ビジョン・ジャパン、日本レスキュー協会、日本エージェンシーの方々。
専門性を生かした報告と提言がなされました。
冒頭、会場には愛子さまのお姿があり、その静かなご登場に参加者の間から驚きと感動の声が上がりました。
緊張感の中にも温かさが広がり、取り組みの大切さを後押ししてくださったように感じられました。
【新潟の取り組み】
まず紹介されたのは、新潟県の平時からの備えです。
令和7年3月に「新潟県災害ボランティア支援センター設置に関する協定」が締結され、
市町村社協やNPOとの連携体制が整備されつつあるとの報告がありました。
役割分担を明確にすることが、災害時の迅速な支援につながることが強調されました。
~三つの柱~
子ども支援
発災直後から「子どもの居場所」を当たり前に設置し、安心・遊び・学び・休息を保障する重要性が訴えられました。
避難所運営の必須事項として明文化する提案もあり、担い手の全国的な育成や調整機能の強化が必要とされています。
ペットを含む世帯支援
「動物そのものの命」だけでなく「飼い主と家族の生活」を守る視点が欠かせないことが共有されました。
同行避難や仮設住宅での受け入れ、自助としての備えやしつけ、公助としての体制づくりの両輪が求められています。
地域コミュニティ再建
被災者が参加しやすい交流の場を設けることの意義が示されました。
体操やワークショップといった小さな活動が会話を生み、やがては自走的なつながりへ。
企業のネットワークやコミュニケーション設計力も地域回復の支えになると提案されました。
セッションを通して見えてきたのは、
・子どもの居場所の早期・標準的な設置
・ペット世帯が安心できる避難・生活継続の仕組み
・交流の場を通じたコミュニティ再建
この三本柱です。行政・社協・NPO・企業が互いの強みを持ち寄り、私たち一人ひとりが「目指す姿」を共有して
平時から備えを進めることの大切さが改めて確認されました。
そして来年の「ぼうさいこくたい」は鳥取で開催されます。新たな地域の学びや出会いに期待が高まります。
みなさまからご質問などありましたら
ぜひ〈できるかもニュースレター〉までお寄せください♪
yamas@kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp
********************************************************************
ジェンダーを含めた「多様性配慮ガイドライン」
災害時、性的マイノリティの方が避難所に行くことをためらう現実があります。
その背景には、プライバシーや偏見への不安など、普段から抱えている課題が映し出されています。
けれども、知り、学ぶことで理解が広がれば、その壁は少しずつ低くなります。
平時から互いを知り合い、尊重し合うことが、いざという時の安心につながります。
誰もが一緒に過ごせる避難所をめざして、今できる学びを重ねていきましょう。
2025年3月にJVOADが作成した多様性配慮のガイドラインをご紹介します。(以下URL)
https://jvoad.jp/wp-content/uploads/2025/04/14393636f4fc8597f627834789367046.pdf
このガイドラインは、災害中間支援組織で活動する被災者支援コーディネーターを対象に作成されていますが、
災害支援の重要な連携パートナーである行政、社会福祉協議会の職員、NPO や企業など、すべての支援関係者が参考とし、
活用することを期待されたものです。
災害時に見えにくかったコトが、JVOAD の「多様性配慮ガイドライン」であらためて浮き彫りになりました。
このガイドラインには、専門用語解説もあります。
オンライン勉強会の開催レポートもご覧いただけます。
「災害の声なき声にどう応えるか—–多様性配慮ガイドラインの実践を考える」(下記URLより)
https://jvoad.jp/news/20250813/
こういった多様性配慮については、災害だけでなく、普段の暮らしのなかで学び、備えておきたい視点だと考えます。
********************************************************************
しものせき防災フェスタ2025
~備えと安心のための・体験・学び・交流~
イベント詳細情報
https://www.kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp/boshu/boshu63931/
チラシはこちら
【開催日時・場所】
2025年10月5日(日) 10:00~14:00
菊川ふれあい会館 アブニール (下関市菊川町下岡枝117)
【主旨・内容】
もしもの災害に備えて。地域で守ろう、みんなの命。
いざという時にパニックにならないため、防災についてのセミナー。
防災訓練やワークによる体験や学び、防災グッズの展示や販売など楽しみながら学んで交流するイベントです。
☆講演(多目的ホール)★ 講演来場者に自衛隊炊事班によるおにぎりを先着300名様にプレゼント!
- 第一弾 10:00~10:50
『私たちの防災』菊川断層について
清末・小月自主防災会 特別アドバイザー/ 中島 昭治氏
- 第二弾 11:10~12:00
『災害関連死ゼロを目指して』
山口県災害看護研究会/ 会長 網木 政江氏
☆活動紹介12:00~12:30
市民活動団体による災害時サポート紹介
しものせき多文化ひろば/下関フットケアの会/点訳サークルあかね/~mother hand’s~このゆびとまれ/Mint
1階
展示室10:00~14:00
非常持ち出し袋 エコノミークラス症候群の予防
ホワイエ10:00~14:00
災害ボランティアパネル展示・募金受付
防災体験・地震体験イベントほか
2階
小・中ホール10:00~14:00
市民活動団体によるワークショップ
研修室10:00~14:00
災害体験VR(中学生以上)
ラウンジ10:00~14:00
ワークショップ(タイルコースター)
パネル展示(県民活動団体などの紹介)
和室12:00~14:00
絵本などの読み聞かせ
屋外ひろば
防災体験&展示
※雨天決行・荒天中止(雨天の場合、屋外イベントは一部変更となります)
中止の場合はセンターHP、インスタグラム、Facebookでお知らせいたします。
みなさま、奮ってご参加ください!
********************************************************************
◆ぼうさい活動に関する助成金情報
★山口県 災害関連・支援制度一覧
「令和7年8月9日からの大雨」により被災された皆様へ~被災者支援のための主な制度
被災された方に対して、様々な支援制度があります。以下、ご覧ください。
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/21/218266.html
★公益財団法人浦上食品・食文化振興財団
「食文化復興支援事業」
・災害復興支援活動(食を通しての雇用創出/防災意識等の普及/災害後の復興支援活動など)
・食文化復興支援活動(食を通して地域の食文化継承/農林水産業連携/食育活動など)
助成上限:【Aコース(単発)】30万/件・【Bコース(通年)】100万/件、助成総額:1000万 ※助成総額拡充
⇒ https://www.urakamizaidan.or.jp/fukkou/index.html
※公募中、受付期間:10/1~10/31〆切
★【日本郵便株式会社】2026年度 年賀寄付金配分による助成公募事業
風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業
※事業範囲内
活動・チャレンジ以外 上限500万円/件
活動・チャレンジ 上限50万円/件
https://www.kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp/jyosei/jyosei64277/
申込〆切 2025年11月7日(金)まで 当日消印有効
★【日本ハム 食の未来財団】2025年度 災害時等における救援活動支援助成
国民の安全・安心な生活に影響を及ぼすような非常災害や非常事態等において、
主として食物アレルギーをはじめとするアレルギー疾患をお持ちの方(要配慮者)に必要とされる救援活動を支援するため
上限:100万円/件
⇒https://www.miraizaidan.or.jp/general_public/relief_grants/2025/01.html
※常時募集
防災に関する助成金情報のほか、
「人と社会 もっと知りたい人へ~NPO活動支援メルマガ☆さぽ~とメール」では、
福祉や子どもの健全育成、まちづくりなど、さまざまな分野の助成金情報も多数掲載しています。
ご希望の方は、下記のメールアドレスまでご連絡ください。
yamas@kenmin.pref.yamaguchi.lg.jp
※メールの件名は「さぽ~とメール申込み」としていただけますと幸いです。
********************************************************************
「できるかもニュースレター」では、今後も防災に関する情報を皆さんと共有し、
みなさんと一緒に、あたたかい情報ネットワークを築いていきたいと思います。
ご意見やご感想もぜひお寄せください。
新規お申込みは下記フォームより
https://forms.gle/RxRSfKjb9awpEHAs6
********************************************************************